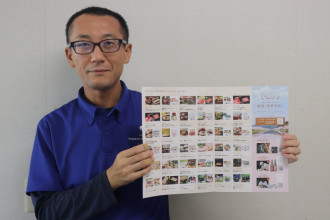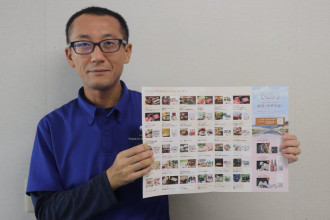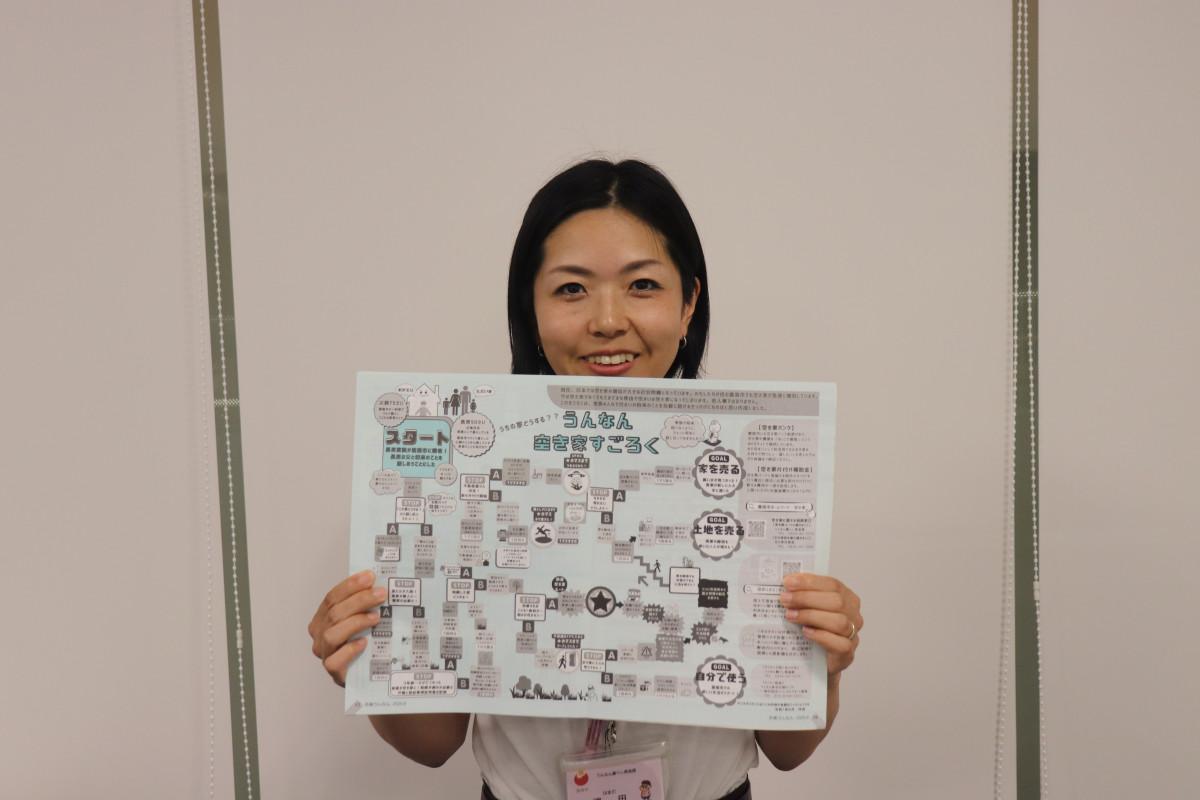戦国時代に始まり今年で451回目を数える「だいとう七夕祭」が8月6日、雲南市大東町大東の街なかで行われ、多くの住民でにぎわった。主催は大東七夕祭保存会。
大東でも戦いが絶えなかった戦国時代、出雲地方を支配していた尼子が毛利に破れ、1573年、毛利輝元の家臣の児玉左衛門が代官として着任したころから大東にも平和が訪れた。安心して暮らせるようになった人々は、翌年の七夕の夜、ササ竹に平和の喜びを表した短冊を飾り付け、太平の世を祝ったことから同祭が始まったとされる。
江戸時代になり、宮田玄祐という寺子屋の師匠が、七夕の前の夜に里芋の葉にたまった露を使って墨をすり、子どもたちが詩歌などを短冊に書いてササ竹に付け、互いに批評させたと伝わる。子どもたちを帰すときにササ竹にちょうちんを付け、行列をして歩かせたところ、それが町中の評判になり、夢多い子どもたちの心に火をつけたと伝えられている。それがやがて大東の七夕の行事となり、自治会ごとに、それぞれちょうちんを手作りし、子どもたちが街を練り歩く子ども行列が行われるようになった。
当日は、露店が多く並ぶ夕暮れの街なかの通りを12地区の子どもたちがちょうちんを手に練り歩き、全てのちょうちんと行列に参加した子どもたちが赤川の堤防に並ぶと、恒例の子ども花火が始まった。同堤防から一列に並んで花火を披露すると、赤川の水面に花火が映り幻想的な風景を作り出し、観客から歓声が上がった。その後、打ち上げ花火が行われ祭りはクライマックスを迎えた。
その後も、街なかでは和野社中による海潮神代神楽が披露されたほか、商工会青年団の模擬店や特産品を販売する店が並び、夜遅くまでにぎわいを見せた。