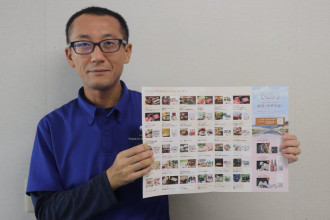雲南で「たたら製鉄」の砂鉄選鉱場跡説明会 市民30人超が参加

雲南市教育委員会文化財課が10月11日、発掘調査を進めている寸丸鉄穴(すまるがんな)砂鉄選鉱場跡(雲南市吉田町川手)で現地説明会を開き、30人以上の市民が参加した。
日本刀の材料となる玉鋼を造る「たたら製鉄」として日本で唯一高殿が残る「菅谷たたら」(吉田町菅谷)に原料となる砂鉄を供給した12カ所の「鉄穴(かんな)」(砂鉄採取場)の中でも主要な砂鉄供給地である寸丸鉄穴は1871(明治4)年に開発され、1882(明治15)年までの12年間、年平均145トンもの砂鉄を算出したという文献が残る。
雲南市教育委員会が、その実態を明らかにするために発掘調査を行い、全長90メートルを超えるその規模と、砂鉄を比重によって水洗選別する施設の構造などが明らかになった。
鉄穴は渓流から引き込んだ水の力で山を掘り崩す大規模な鉱山。砂鉄を含んだ花こう岩の風化土を掘削した「切羽」と呼ばれる場所は、寸丸鉄穴では標高280メートル前後の場所にあり、現在は山が切り崩されてなだらかになっている。切り崩された花こう岩の風化土は、切羽から選鉱場までは標高差が140メートルある「走」と呼ばれる水路を流れ落ちる間に細かく粉砕され砂鉄と砂の分離が進み、選鉱場へと導かれる。
選鉱場は、上流から砂溜1、砂溜2、大池、乙池、中池、樋(とい)から成り、いずれも石組みで構築され、砂鉄と砂の比重の違いを利用して砂鉄と砂を分離した。各池の間には「管」という木棒を積んだ仕切りがあり、管を超える砂混じりの流水は排砂溝より排出され、中にたまった土砂は比重の重い砂鉄が比較的多く、清水路より水を入れて管を外すことで、砂鉄を含む比重の重い土砂を次の池に移した。これを上流から繰り返すことで砂鉄の含有量を高めたという。
当日は、同課課長の角田徳幸さんが選鉱場の最下部で概要を説明し、その後、参加者を選鉱場最上部まで案内。上部から順に選鉱場の構造や機能などを詳しく説明した。最後には同選鉱場が神社の境内に造られたことを表す神社の遺構も説明した。神社の遺構には江戸時代の年号が刻まれたちょうず場があることから、神社が先にあり、その後、選鉱場が造られたことなどを解説した。
角田さんは「調査が終了後、保存のためいったん埋め戻すが、将来はたたら製鉄の文化を伝える遺跡公園として整備し、市民に見てもらえるようにしたい」と話す。